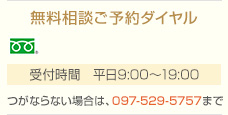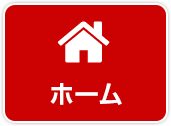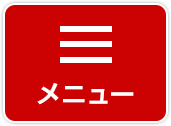非上場の自社株を相続して“相続税が払えない”後継者がとるべき対策を税理士が解説
こんにちは!大分の税理士事務所「イデア総研税理士法人」の代表税理士、南徳行です。
私は日頃、大分で多くの相続や事業承継のご相談をお受けしています。
その中でも特に深刻なご相談の一つが、「先代が亡くなって自社株を相続したけれど、相続税が高すぎて払えそうにない」という後継者の方からのお悩みです。
会社は黒字で、地域や従業員の生活を支えている。それなのに、後継者が相続税を払えないために会社が傾いてしまうかもしれない…。
これは、会社にとっても、後継者にとっても、そして先代経営者にとっても、非常につらい状況ですよね。
この記事では、なぜ非上場株式(自社株)の相続税が払えなくなるのか、その理由と、万が一「払えない」状況に直面したときの対処法、そして最も重要な「そうならないための事前対策」について、相続の専門家である税理士の視点から分かりやすく解説します。
1. なぜ「自社株の相続税を払えない」状況になるのか?
「会社は儲かっているのに、相続税が払えない」という事態は、多くの中小企業の後継者が直面する可能性のある大きな課題です。
その主な理由は、非上場株式が持つ「2つの厄介な性質」にあります。
一つ目は、評価額が非常に高くなりやすいことです。
非上場株式には市場価格がないため、相続税を計算するときは国税庁のルール(財産評価基本通達)に基づいて株価を評価します。
業績が好調で、長年利益を積み上げてきた優良企業ほど、会社の純資産は大きくなります。
その結果、後継者が相続する自社株の評価額も、想像をはるかに超える金額になるケースが多いのです。
二つ目は、換金性が著しく低いことです。
上場株式であれば、証券取引所ですぐに売却して現金に換えられます。
しかし、非上場株式は買い手を見つけるのが非常に困難です。
相続税は、原則として「相続開始から10ヶ月以内に現金で一括納付」しなければなりません。
つまり、後継者は「評価額は高い(=相続税は高額)けれど、売って現金に換えることができない(=納税資金がない)」という深刻なジレンマに陥ってしまうのです。
2. 相続税を払えないときに検討すべき2つの対処法
もし事前対策が間に合わず、相続が発生して「相続税が払えない」という現実に直面してしまった場合、どうすればよいでしょうか。
法的に認められている、相続発生後の主な対処法(納税手段)は「延納」と「物納」の2つです。
対策1:延納(分割払い)
延納とは、相続税を現金で一括納付することが難しい場合に、税務署の許可を得て、分割で納付する制度です。
メリット:
・当面の納税資金がなくても、分割払いで時間を稼ぐことができます。
・担保として、相続した非上場株式そのものを充てることが可能です。
デメリット・要件:
・「金銭で納付することを困難とする事由」を証明する必要があります。
・原則として、延納税額に見合う担保の提供が必要です。
・延納期間中は、利子税という利息をあわせて納付しなければなりません。
延納は、要件を満たせば比較的認められやすい一般的な対処法です。
しかし、利子税の負担が長期的に会社のキャッシュフローを圧迫する可能性も考慮する必要があります。
対策2:物納(モノで納める)
物納は、延納を使っても現金での納税が困難な場合に、その困難な金額を限度として、相続財産そのもの(現物)で税金を納める制度です。
極めて厳格な要件:
物納が認められるハードルは非常に高いです。まず、「延納によっても金銭で納付することが困難」であることが絶対条件です。
非上場株式の劣後性:
物納できる財産には優先順位が定められています。不動産や上場株式が第1順位であるのに対し、非上場株式は第2順位です。他に第1順位の財産があれば、そちらを先に物納に充てる必要があります。
最大の障壁:「管理処分不適格財産」
国が管理・処分するのに適さない財産は物納できません。多くの中小企業株式は「譲渡制限」がついており、これが「管理処分不適格」と判断される場合があります。
実際、物納の許可件数は全国でも極めて少なく、専門家の立場からすると、非上場株式による物納は「現実的な選択肢とは言い難い」のが実情です。
3. 「払えない」を防ぐための事前対策と株価引き下げのポイント
ここまで解説した延納や物納は、あくまで相続が起きてしまった後の「対症療法」です。事業承継で最も重要なのは、先代経営者がお元気なうちから計画的に準備を進める「予防策」です。
「払えない」事態を防ぐ対策は、大きく「納税資金を準備する対策」と「相続税そのものを減らす対策」に分けられます。
特に効果的なのが「相続税そのものを減らす対策」、すなわち「自社株の評価を引き下げる」ことです。
株価の評価方法は複雑ですが、その評価額は会社の利益や純資産に連動しています。
つまり、合法的な対策によって利益や純資産を適正に変動させることで、株価の評価額を適正に引き下げることが可能です。
ポイント1:生前贈与の活用
株価が低いタイミングを見計らって、後継者に生前贈与する方法です。
・暦年贈与: 年間110万円の基礎控除の範囲で少しずつ贈与します。
・相続時精算課税制度: 2,500万円までの特別控除枠があり、贈与時の株価で評価額を固定できるため、将来の株価上昇が見込まれる場合に有効です。
ポイント2:役員退職金の支給
先代経営者が退職する際に、適正な役員退職金を支給します。
会社にとっては大きな経費(損金)となり、純資産も減少するため、株価を引き下げる効果が期待できます。
ポイント3:持株会社(ホールディングス)の活用
持株会社を設立するスキームを活用すると、事業会社の株式評価額に含まれる含み益に対して法人税等相当額(約37%)を控除できるため、適正な方法で評価額を引き下げられる場合があります。
これらの対策は、実行するタイミングや組み合わせが非常に重要であり、高度な専門知識を要します。
4. 専門家に相談するメリットと無料相談で確認すべきこと
「自社株の対策が必要なのは分かったけれど、何から手をつければ…」と不安に思われるかもしれません。
事業承継や自社株対策は、相続税だけでなく、法人税、所得税、さらには会社法まで絡み合う、非常に専門的な分野です。
専門家に相談するメリット
税理士などの専門家に相談する最大のメリットは、自社の状況に合わせた最適な対策を、組み合わせて提案(オーダーメイド)してもらえることです。
例えば、
● 納税資金を確保するために「生命保険」を活用する。
● 要件を満たせば納税が猶予・免除される可能性がある「事業承継税制(特例措置)」の適用を検討する。
● 相続トラブルを防ぐために「種類株式」を活用して、議決権と財産権を分離する。
これら多様な選択肢の中から、会社の将来像や後継者の意向を踏まえた「わが社だけの承継プラン」を一緒に作っていくパートナーが専門家です。
初回無料相談などで確認すべきこと
多くの税理士事務所では、初回相談を無料(※)で行っている場合があります。
(※時間制限や相談内容に条件がある場合もあります)その機会にぜひ確認していただきたいのは、以下の点です。
1. 自社の株価評価の概算: 今、相続が起きたら、自社株はいくらと評価されそうか。
2. 事業承継・自社株対策の実績: 似たような業種や規模の会社の対策を行った経験が豊富か。
3. 対策の選択肢: 自社の場合、どのような対策が考えられそうか、そのメリット・デメリットは何か。
4. 人柄と相性: これから長期的に会社の未来を相談する相手として、信頼できるか、話しやすいか。
まとめ:事業承継は「早めの準備」が成功の鍵です
非上場の自社株を相続して「相続税が払えない」という事態は、決して他人事ではありません。
それは事業が不調だから起こるのではなく、むしろ事業が成功し、利益を積み上げてきた優良企業だからこそ直面する問題なのです。
しかし、この記事で解説した通り、この問題は「回避可能な問題」でもあります。
相続が発生した後の「延納」や「物納」といった対処法には限界があります。
本当に後継者と会社を守るためには、先代経営者がお元気なうちから、計画的に対策を進めることが不可欠です。
納税資金を確保するための生命保険の活用や自己株式の取得。
納税を猶予・免除する可能性がある事業承継税制の活用。そして、株価そのものを適正化する生前贈与や組織戦略。
どの対策が最適かは、会社の状況や経営者のお考えによって全く異なります。
私たちイデア総研税理士法人は、ここ大分で「お客様の繁栄と幸せを創造する」という理念のもと、これまで多数の企業の事業承継支援に携わってきました。
先代が大切に育ててきた会社を、万全の体制で次の世代へ引き継ぐ。
そのお手伝いをさせていただくことが、私たちの役割だと考えています。
「うちの会社は大丈夫だろうか?」「何から相談すればいいか分からない」
少しでも不安を感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。
まずは現状をお聞かせいただき、一緒に未来のための準備を始めましょう。

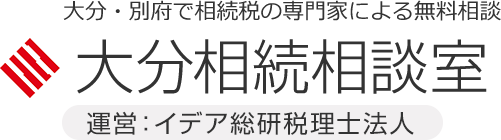
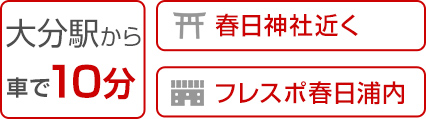
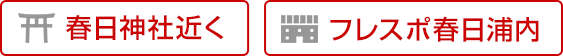
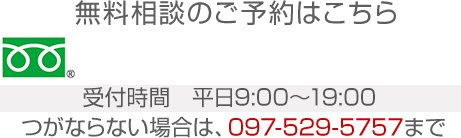

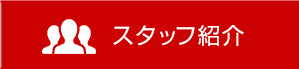




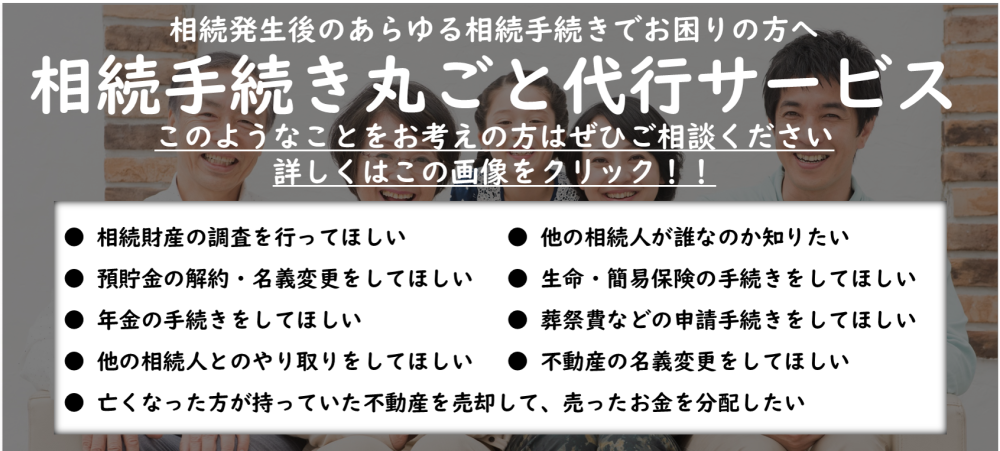
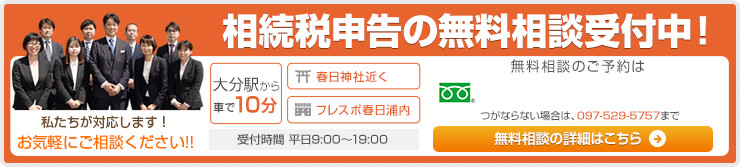 0120-718-737
0120-718-737