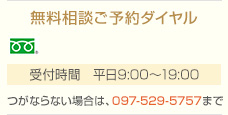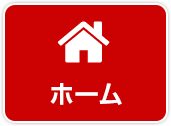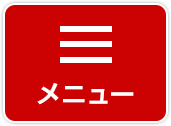相続税の税務調査に備える!税務署の調査対象となる年度・状況と、今からできる対策
【監修】イデア総研税理士法人 代表税理士 南 徳行
大分の税理士事務所「イデア総研税理士法人」の代表税理士、南徳行です。
この度は、当事務所のコラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。相
続に関する手続きは、ただでさえ複雑で心労も重なるもの。
それに加えて「税務調査」と聞くと、「なんだか難しそう…」「うちは大丈夫だろうか?」と不安に思われる方も少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は「相続税の税務調査に備える!税務署の調査対象となる年度・状況と、今からできる対策」というテーマで、皆さまの疑問や不安を解消できるよう、分かりやすく解説してまいります。どうぞ、肩の力を抜いてお読みくださいね。
税務署が相続税調査を行う理由とは?
まず、なぜ税務署は相続税の税務調査を行うのでしょうか。
その大きな目的は、「申告内容が正しいかどうかの確認」と「課税の公平性を保つこと」の2点にあります。
相続税は、亡くなられた方(被相続人)から財産を受け継いだ人が、その財産の価額をもとに自ら計算して申告・納税する「申告納税制度」が採用されています。
しかし、残念ながら、申告された内容がすべて正しいとは限りません。
中には財産を意図的に隠したり、評価額を低く見積もったりするケースもあれば、単純な計算ミスや知識不足から申告漏れが生じてしまうケースもあります。
このような申告漏れや誤りを見つけ出し、正しく納税してもらうことで、正直に申告した人が不公平感を感じることのないように、税務署は調査を行っているのです。
国税庁が公表した最新の令和5事務年度のデータによると、相続税の実地調査件数は8,556件、そのうち申告漏れ等の非違(誤りなど)があった件数は7,200件に上ります 。これは、調査が入ったケースの84.2%で何らかの指摘があったことを意味し、依然として高い割合です 。
実地調査の件数は前年度から増加しており 、相続税の税務調査は決して他人事ではない実態がうかがえます。
相続税調査の対象になりやすいケース
では、具体的にどのような状況だと、税務調査の対象になりやすいのでしょうか。
税務署は、過去の申告データや独自の情報網(国税総合管理システム(KSK)など)を駆使して、あらゆる角度から申告書をチェックしています。
ここでは、特に調査対象となりやすい特徴的なケースをいくつかご紹介します。
①相続財産の総額が大きい
これは最も分かりやすい特徴です。
当然ながら、相続財産の金額が大きければ大きいほど、申告漏れがあった場合の追徴税額も高額になります。
そのため、税務署としても調査の費用対効果が高くなり、一般的に財産総額が大きい場合は調査の可能性が高まる傾向があります。
②申告書の内容に不備や矛盾点がある
提出された申告書の内容に、計算ミスや記載漏れ、添付書類の不足などがあると、「この申告は本当に大丈夫だろうか?」と税務署に疑念を抱かせるきっかけになります。
また、被相続人の生前の所得や職業などから考えて、申告された相続財産が明らかに少ないといった矛盾点がある場合も、調査の対象になりやすい状況と言えるでしょう。
③名義預金・名義株が疑われる
「名義預金」とは、例えば「専業主婦である奥様名義の預金口座に、ご主人の給料から毎年100万円ずつ入金されていた」といったように、口座の名義人と実際にお金を管理・拠出していた人が異なる預金のことです。
たとえ名義が配偶者やお子様、お孫様のものであっても、その原資が被相続人のお金であれば、それは被相続人の財産として相続税の対象となります。
税務署は、過去の所得状況やお金の流れを詳細に把握しているため、こうした名義預金は特に厳しくチェックされるポイントです。
④海外に資産がある、または評価が難しい財産がある
海外資産は国内資産に比べて実態の把握が難しいため、申告から漏れやすい財産の一つです。
また、非上場株式や広大な土地、骨董品など、評価方法が複雑で専門的な知識を要する財産が含まれている場合も、その評価額が適正かどうかを確認するために調査の対象となることがあります。
相続税調査の具体的な流れと調査内容
実際に税務調査が行われる場合、どのような流れで進むのでしょうか。一般的な流れと調査内容を知っておくことで、いざという時も落ち着いて対応できます。
【調査の流れ】
1. 事前通知
多くの場合、調査が行われる数週間前に、税務署の担当者から税理士(申告を依頼している場合)または相続人代表者へ電話で連絡が入ります。
「相続税の申告内容についてお尋ねしたいことがありますので、○月○日にご自宅へお伺いしてもよろしいでしょうか」といった形で、調査日時が調整されます。
2. 実地調査
約束の日時に、通常2名ほどの調査官が自宅を訪問し、1~2日間にわたって調査が行われます。
調査では、まず被相続人の人柄や趣味、生前の生活状況など、世間話のような形でのヒアリングから始まります。
これは、申告されていない財産の手がかりを探るための重要なプロセスです。
3. 調査後のやり取り
実地調査で生じた疑問点について、後日、税務署から税理士等を通じて問い合わせがあります。
ここで的確な説明ができないと、申告漏れを指摘されることになります。
最終的に非違事項が認められれば、修正申告書を提出し、追加の税金(延滞税や過少申告加算税など)を納付することになります。
【主な調査内容】
● 預金通帳の確認: 被相続人だけでなく、相続人全員の過去10年分程度の預金通帳の動きを細かく確認し、不審な入出金がないかチェックします。
● 現物確認: 自宅内の金庫や仏壇、タンスの中などを確認し、現金(いわゆるタンス預金)や貴金属、有価証券などがないか調べることがあります。
● ヒアリング: 被相続人の交友関係やお金の使い方、趣味などについて詳しく質問されます。
相続税調査への準備と対策方法
ここまで読むと、「調査はやっぱり怖い…」と感じてしまうかもしれません。
しかし、ご安心ください。しっかりと準備と対策をしておけば、過度に恐れる必要はありません。大切なのは、誠実な姿勢で臨むことです。
【生前からできる対策】
財産目録の作成
ご自身が元気なうちに、預貯金、不動産、有価証券、生命保険といったプラスの財産から、借入金などのマイナスの財産まで、すべてを一覧にした「財産目録」を作成しておくことを強くお勧めします。
これにより、相続人が財産を把握しやすくなり、申告漏れのリスクを大幅に減らすことができます。
生前贈与の記録を明確に残す
生前贈与を行う際は、贈与の事実を客観的に証明できるよう、「贈与契約書」を作成しましょう。
また、手渡しではなく銀行振込を利用し、通帳に記録を残すことが重要です。
【申告時にできる対策】
相続税に強い税理士に相談する
相続税申告は非常に専門性が高く、税理士によって経験や知識に差があります。
私たちのような相続を専門とする税理士に相談することは、安心できる有効な対策の一つです。
税務署がどのような点をチェックするのかを熟知しており、適正な財産評価と正確な申告書作成をサポートします。
「書面添付制度」を活用する
これは、税理士が「この申告書は、私たちが責任をもって内容を精査し、適正に作成しました」というお墨付きの意見書を申告書に添付する制度です。
この書面が添付されていると、税務署からの信頼度が上がり、実地調査の前に税理士へ意見を聴取する機会が設けられるため、結果として実地調査が省略される可能性もあります。
もちろん、私たちイデア総研税理士法人でも、この制度を積極的に活用しています。
まとめ|不安を安心に変えるために
今回は、相続税の税務調査について、その実態から対策までを解説しました。
税務調査は、決して特別な人だけが対象となるものではなく、誰にでもその可能性はあります。
令和の時代においても、その重要性は変わりません。
しかし、その一方で、誠実に財産と向き合い、専門家のサポートを受けながら適正な申告を行えば、何も恐れることはないということも、ぜひ知っておいていただきたいのです。
相続とは、単なる事務手続きではありません。
それは、故人様が生涯をかけて築き上げてこられた大切な財産と、ご家族への「想い」を、次の世代へと繋いでいくための、非常に尊い手続きです。
その大切なプロセスが、税務調査への不安や追徴課税といった問題で、後味の悪いものになってしまうのは、あまりにも悲しいことです。
私たち大分の「イデア総研税理士法人」は、単に税金の計算をするだけではありません。
お客様一人ひとりのご家庭の状況や想いに深く寄り添い、円満な相続を実現するため、持てる知識と経験のすべてを尽くしてサポートすることをお約束します。
私たちの仕事は、皆さまの不安を安心に変えることだと考えています。
「うちの状況は調査の対象になるのだろうか?」「生前の対策として、何から始めたらいいか分からない」など、少しでもご不安や疑問に思うことがございましたら、どうか一人で抱え込まず、お気軽に私たちにご相談ください。あなたの、そしてご家族の未来のために、最善の道筋を一緒に見つけていきましょう。
【出典】
国税庁「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」

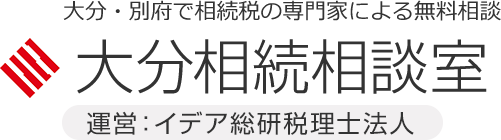
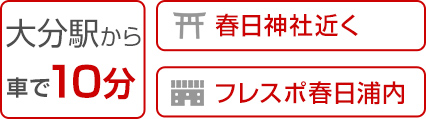
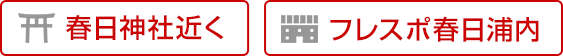
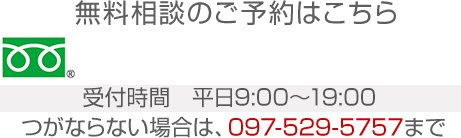

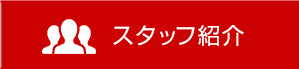




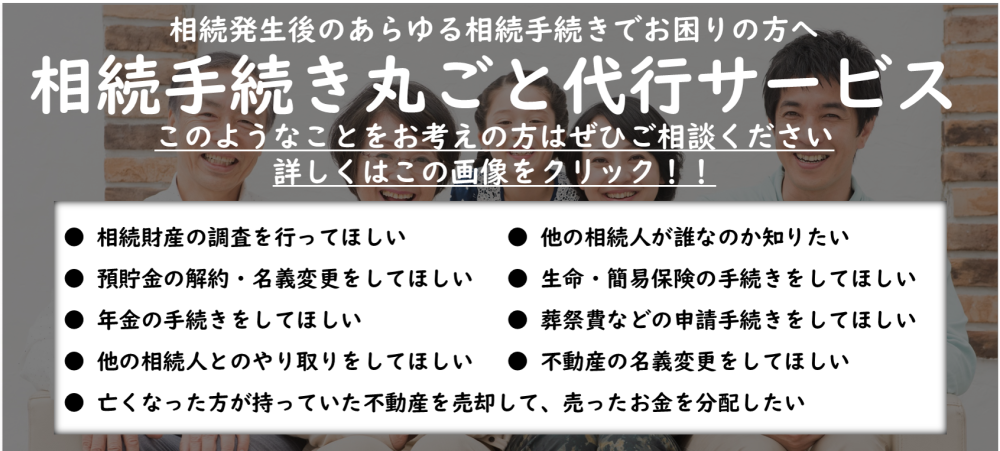
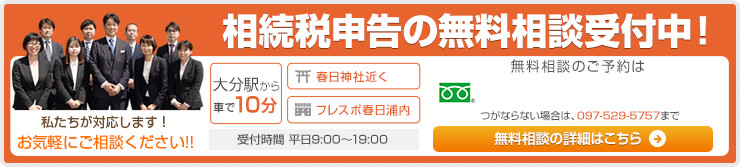 0120-718-737
0120-718-737