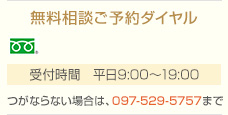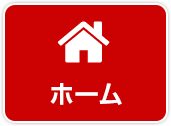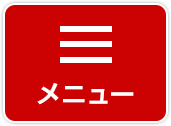相続税申告で損をしないための節税対策5選|専門家が解説する申告ポイントと特例活用法
【監修】イデア総研税理士法人 代表税理士 南 徳行
こんにちは。大分の税理士事務所 イデア総研税理士法人 の南徳行です。
「相続税、うちはいくらかかるんだろう?」「財産をできるだけ多く家族に残したいけど、何から始めれば…」
相続は、いつか必ず訪れるものですが、多くの方にとって初めての経験であり、不安や疑問が尽きないのではないでしょうか。特に相続税については、知らないままでいると、本来納めなくてもよかったはずの税金を支払ってしまうケースも少なくありません。
この記事では、皆様の大切な財産を円満に次世代へ引き継ぐため、相続税の節税対策について、ポイントを絞って分かりやすく解説します。
1. 相続税節税対策の基本を理解する
相続税の節税対策と聞くと、何か特別な裏技をイメージされるかもしれませんが、基本はとてもシンプルです。
それは**「課税対象となる財産を減らすこと」と「使える特例や控除を漏れなく活用すること」**の2つに集約されます。
相続税は、亡くなった方の財産(遺産総額)から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額に対して課税されます。
つまり、この遺産総額そのものを生前のうちから計画的に減らしておくか、相続発生後に適用できる特例などを最大限活用することで、
納税額を抑えることが可能になるのです。大切なのは、ご自身の財産状況を正しく把握し、一日でも早く対策を始めることです。
2. 相続税を減らすための主な方法【5選】
相続税を減らすための具体的な方法は多岐にわたりますが、ここでは特に活用しやすく効果の高い5つの方法を厳選してご紹介します。
①生命保険の非課税枠を活用する
死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象になりますが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
ただし、この非課税枠が使えるのは、受取人が法定相続人の場合に限られるため注意が必要です。
納税資金の準備と節税を同時に実現できる有効な方法です。
②小規模宅地等の特例を活用する
ご自宅や事業で使っていた土地の評価額を、一定の要件のもと最大80%も減額できる強力な特例です。
例えばご自宅の土地であれば330㎡までの部分について適用できます。
適用要件が非常に複雑なため、専門家の判断が不可欠です。
③生前贈与で財産を移転する
暦年贈与の年間110万円の非課税枠を使い、計画的に財産を贈与していく方法です。
時間をかけるほど大きな節税効果が期待できます。
④不動産を活用した評価額対策
現金を不動産に換えることで、相続税評価額を時価よりも低く抑えられる場合があります。
ただし、借入金を伴う場合の返済負担や、空室・不動産市場の変動といったリスクも考慮した上で、慎重に検討する必要があります。
⑤配偶者の税額軽減を最大限活用する
配偶者が相続する財産は、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。
ただし、二次相続(その配偶者が亡くなった時の相続)まで見据えた分割が重要です。
3. 生前贈与の節税効果と注意点
生前贈与は、相続税対策の王道ともいえる方法です。
年間110万円の非課税枠を使えば、10年間で1,100万円、20年間で2,200万円もの財産を非課税で次世代に移すことができます。
ただし、注意点も存在します。2024年からの税制改正により、亡くなる前7年以内に行われた贈与は相続財産に持ち戻して計算されることになりました(以前は3年)。
また、贈与の事実を証明できない「名義預金」は、税務署から故人の財産とみなされ、追徴課税の対象となるリスクがあります。
生前贈与を有効に活用するためには、贈与契約書を作成し、銀行振込で記録を残すなど、法的に有効な形で実行することが何よりも大切です。
4. 相続税対策の成功事例と失敗事例
ここでは、対策の有無がどのような結果の違いを生むのか、簡単な事例で見てみましょう。
【成功事例】
Aさんは、60代の頃から税理士に相談し、計画的に相続対策を開始。
自宅については「小規模宅地等の特例」が使えるよう、長男との同居を継続。
また、年間110万円の暦年贈与を子ども2人に行い続け、生命保険の非課税枠も活用しました。
その結果、Aさんの相続が発生した際、納税額を数百万円単位で圧縮でき、家族は慌てることなく円満に相続を終えることができました。
【失敗事例】
Bさんの相続(一次相続)が発生した際、ご家族は「配偶者の税額軽減」を使えば税金がゼロになると知り、全ての財産を配偶者である奥様が相続しました。
その結果、一次相続の納税額は0円に。
しかし数年後、その奥様が亡くなり二次相続が発生した時には、財産が奥様一人に集中していたため基礎控除額を大幅に超え、さらに配偶者の税額軽減も使えず、子ども達が想定以上の高額な相続税を負担することになりました。
一次相続の際に、二次相続まで見据えて専門家と分割協議をしていれば、家族全体の納税額を大きく減らせたはずです。
5. 相続税節税対策を専門家に相談すべき理由
「節税対策は自分で探してできそうだ」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続税の申告と対策は、専門家である税理士に相談することを強くお勧めします。その理由は主に3つあります。
第一に、相続税法や特例の適用要件は非常に複雑で、頻繁に改正も行われます。
知識が不十分なまま判断すると、特例を使えなかったり、申告漏れを指摘されたりする危険性があります。
第二に、ご家庭ごとに財産状況や家族構成は全く異なります。
インターネットの記事で見た対策が、必ずしもご自身にとって最適とは限りません。
専門家は、全体を俯瞰し、二次相続まで見据えたオーダーメイドの対策を提案できます。
そして何より、相続はご家族にとって精神的な負担も大きいものです。
信頼できる専門家を探し、味方につけることで、手続きの不安から解放され、心穏やかに故人を偲ぶ時間を持つことができるはずです。
6. まとめ
ここまで相続税の節税対策について解説してきましたが、最も重要なポイントは**「早期の準備」と「専門家への相談」**に尽きます。
相続は、単なる税金の問題ではなく、ご家族の想いを未来へつなぐ大切な手続きです。
生前の元気なうちからご自身の財産と向き合い、ご家族と話し合うきっかけを持つことが、何よりの「対策」と言えるでしょう。
この記事を読んで、「うちの場合はどうだろう?」と少しでも気になった方は、ぜひ一度、お近くの相続に強い税理士事務所の扉を叩いてみてください。
私たちイデア総研税理士法人は、大分という地で、これまで多くのご家族の相続に寄り添ってまいりました。
難しい専門用語ばかりでなく、皆様一人ひとりの心に寄り添い、最適な解決方法を一緒に探すパートナーでありたいと願っています。
初回のご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお声がけください。
あなたの、そしてご家族の未来のための第一歩を、私たちが全力でサポートいたします。

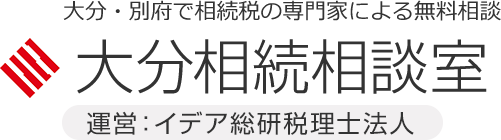
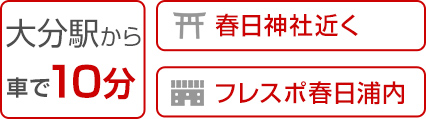
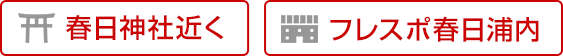
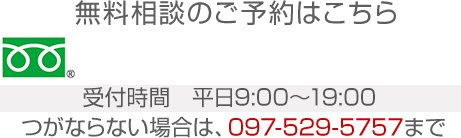

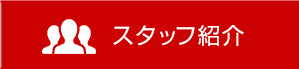




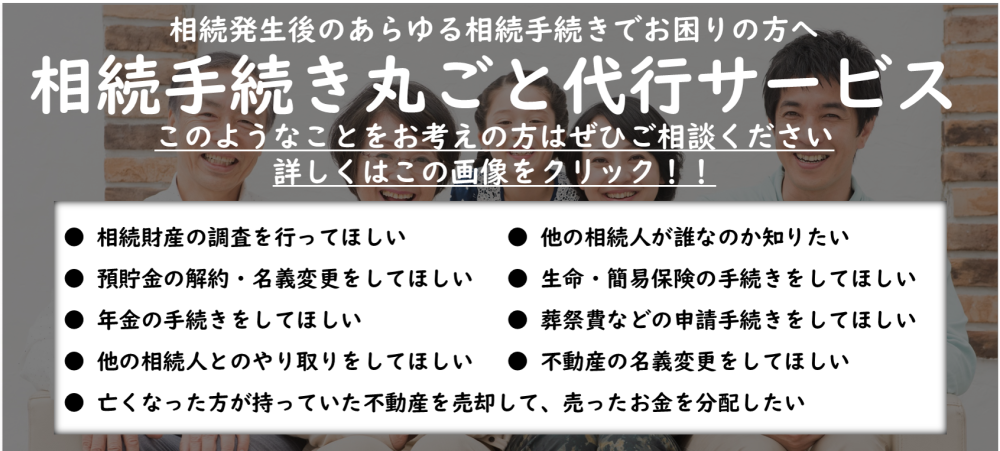
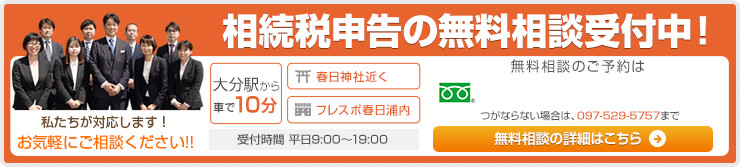 0120-718-737
0120-718-737